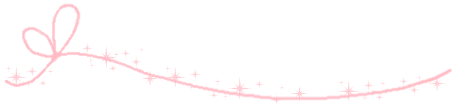
Thank you and you must be happy!!
はいごからじゃなくて
ちかづいたそのときから
ふたりではんぶんこ (現代)
わたしときみと (現代)
▼ はいごからじゃなくて
背後からのし掛かられた重みに、「三郎、暑いんだけど」と抗議したけど、「んー」と語尾を伸ばした返事が戻ってくるだけだった。ちっとも離れそうにない気配に苦笑をこぼし、僕は握っていた筆を文机にある硯に浸ける。とっぷりと、墨の匂いが広がった。夏休みの課題を終え、久しぶりに学園に戻ってきたら、これだ。すぐに報告書を書いて提出しなきゃいけないのは三郎だって分かってるくせに、こうやって邪魔してくる。
「夏休みも終わっちゃうね」
眼前に広がる書面を見やりながら、背中の熱に話しかけると、また「んー」と曖昧な声だけが返ってきた。首がくすぐったい。僕の髪に顔を埋めた三郎の息が吹きかかっているのだろう。
「どうしたのさ」
「…笑わないかい」
珍しく弱々しく訊ねてきた三郎に、こっそりと笑みを堪えながら「笑わない」と答えた。すぐさま、「今、笑ってるし」と指摘が飛んできて、慌てて緩む口の端を引き上げる。
「笑わない。約束する」
で、どうしたの、と続きを促すと、背中にすがる指先がひときわ強くなった。
「おかえり」
「え?」
「だから、おかえりって言ってなかっただろ」
思わぬ言葉に僕の手から筆が滑り落ちた。白い半紙に黒点が散るのも構わず、背中の熱を引き剥がす。三郎ときちんと向かい合う。
「ただいま」
▼ちかづいたそのときから
入学した興奮が冷めやらぬまま、その日、僕は床についた。まだ、心臓がドキドキしている。無事、学園に入学できた喜びと、これからやっていけるか不安で、頭の中がいっぱいで、なかなか眠気が誘われない。おまけに、あてがわれた布団がだ肌に馴染まなくて、僕はなかなか寝付けなかった。寝なきゃ、と思えば思うほど、目が冴えてくる。ごそごそと、布団の中でのたうち回っていると、
「寝れない?」
唐突に響いた声に心臓が口から飛び出るかと思った。すっかり、二人部屋だということを忘れていた。苛立ちの含む声にしまった、と後悔を募らせ謝罪する。
「あ、ごめん。えっと、」
「はちや」
本人に言われて、同室の彼がそんな名字だったことを思い出す。最初の学活で自己紹介もままならないのに、「このクラスにはちやの家柄の奴がいるんだな。なら、はちや、お前学級委員な」と担任に指名されていて覚えた彼だ。
「本当にごめんね、はちや君。なんか一人になるの初めてだからさ、ドキドキしすぎちゃって。」
寝れなくて、と慌ててまくし立てる僕にはちや君は「別にいいけど」と返してくれた。それがうれしくて、つい、「ねぇ、はちや君はどうしてこの学園に入ったの?」と聞いていた。すると、暗闇に呆れたような声が戻ってきた。
「はちやって知らないのか?」
「はちやくんの名字でしょ?」
「そうじゃなくて、はちやっての」
「知らない。あ、そうだ、はちやくんの名前、教えてよ」
しばらく静寂が続き、それから柔らかな声が僕へと届いた。
「三郎。君の名前は?」
▼ふたりではんぶんこ
窓の向こうに、彼がいた。大きなガラスドアが左右に分かれた途端、冷えついた空気がどっと溢れかえってきた。看板と同じ色合いの服を着た店員がチラリと視線を投げ、「いらっしゃいませー」「いらっしゃいませ」と掛け合いを演じる。その自動ドアのすぐ近くの大きな箱の前で、真剣な面持ちで立ち尽くしている彼へと足を向ける。
「雷蔵」
背後に立っても全く気づかない程迷っている彼の肩を、ぽん、と叩くと、びっくりした表情で彼が振り向いた。
「三郎!? どうしたのさ?」
「雷蔵が見えたからさ。アイス?」
「うん。こっちのカップアイスにしようかと思ったんだけど、そっちのチョコがかかったコーンのも捨てがたいなぁと思って」
開けっぱなしにすると中の温度が上がって溶けてしまうのを危惧したのだろう、うっすらと白く曇って中が見えないショーケースに顔を張り付けながらいる雷蔵に答えた。
「じゃあ、半分こしよう」
「えっ、でも」
戸惑う雷蔵に断られる前に、とショーケースを力任せに開け、さっき指差していた2つのアイスを取り出した。
「二人で半分こした方がいいだろ」
▼わたしときみと
雷蔵の枕元で携帯が激しくシャウトしだした。午前5時45分。いつもの通り、そのアラームが途切れることはない。いい加減覚えてしまった音程が3回目になった所で雷蔵のところに向かう。うつぶせになって、顔を枕に預けていた。顔はふわふわな髪に覆われて、表情は見えない。けど、苦しくないんだろうか?
「雷蔵、朝だぞ」
「ん、大丈夫」
ちっとも大丈夫じゃない言葉に、腰のあたりでヤドカリみたいに山になっていたタオルケットを引き剥がす。そのまま、目一杯の力で揺さぶった。首が多少ガクガクしたけど、そんなの構っちゃいられない。そうでもしなきゃ、起きれないのだ。
「雷蔵、遅刻するぞ」
「ん、わかった」
「朝飯、食べれなくなるぞ」
「いいよ」
「置いてくぞ」
「いいよ」
「キスするぞ」
最後の台詞に、がばっと起き上がった雷蔵と目があった。
「おはよう」
← top